
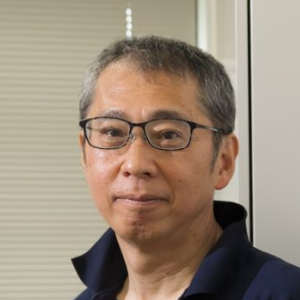
生命倫理は、科学や技術の発達の最前線で「生命とは何か」「人間とは何か」を問うきわめてエキサイティングな学問です。安楽死、自殺幇助、不死、クローン人間、遺伝子の改変、ゲノム編集、人間のサイボーグ化、トランスヒューマン(Transhuman)等々に関する問題が扱われます。人間のあり方、生命のあり方が根本的に変わっていく時代の中で、人間とは何かを問い直しています。生命倫理を学び、知的な刺激を味わいましょう。

ドイツ語学科では、ヨーロッパ政治経済論とドイツ政治研究といった科目を担当しております。ヨーロッパの方はEUや構成国の歴史や現代の政治経済を、ドイツの方では、政治制度や昨今の事情について講義をしております。演習では、学生がヨーロッパやドイツの政治や経済に関する任意のテーマでゼミ論文や卒業論文の執筆を勧めております。研究テーマはドイツの政党や議会政治で、国会議員のリクルートメントや政党の活動を日本との比較を通して見ています。

日本と国際的な立ち位置が類似し、多くの課題を共有しつつ、全く異なる対応を取ることが多いのがドイツ(語圏)です。なので、ドイツ語圏の社会について研究することは、異なる可能性を知って思考を柔軟にするためにも、日本の来し方行く末を考えるうえでも、きわめて意義が大きいと考えています。自分が関心あることを、ドイツ語圏を参照しつつ考えてみると、思わぬ発見があるに違いありません。

大学時代は人生で最も自由な時期だと思います。これからの4年間ほど融通が効き、自由な時間は他にないかもしれません。自由を活用してください!新しいことを学び、興味のあること、楽しいこと、得意なことを見つけ、可能であれば海外に出て世界を見て、異文化を経験してください。私はその道を歩むあなたを応援したいと思います。

情報化社会において、私たちは非常に多様なメディアに囲まれているにも関わらず、日常的に受容する情報コンテンツは極めて限定的です。 このような状況の中で、ある1つのテーマに関する情報は異なる地域において、どのように発信・描写され、人々に受容されているのでしょうか?それらを比較した時に、どのような差異・共通点が見えてくるのでしょうか。 クロスカルチュラルメディア比較の分野ではその疑問を出発点とし、異なる地域と言語における メディアコンテンツの相違点を分析した上で、それぞれの地域における文化や社会情勢の特徴、メディアの実態と課題を明らかにしていきます。メディアの比較と分析を通して、物事を相対的・批判的に捉える視点を共に身に着けていきませんか。

外国語を学んだり使ったりしていると、よくわからないこと、不思議に思うことがいろいろと出てきますね。この語句とこの語句はどういう順序で並べればよいのだろう、なぜそういう語順なのだろう。意味がよく似ている二つの語、どこがどう違っていて、どう使い分ければよいのだろう。伝えたいことがあって、ある語句を使ったら、それは不自然だと言われたけれど、何がまずいのだろう。こうした素朴な疑問を「なんとなく」で終わらせずに研ぎ澄ませていけば、すでに本格的な言語研究の始まりです。英語と兄弟のような関係にありながら何かと違いも目立つドイツ語を手がかりに、ことばとじっくり向き合う面白さを体験してみませんか。

現代では、言語の勉強は時代遅れのように思えるかもしれません。結局のところ、コンピュータはすべてを訳してくれるでしょう。しかし、言語は単なる言葉や感情のない情報ではありません。文化・感情・世界観やアイデアを表現し伝えるものです。言葉の壁を越えて理解し合うことで、ビジネスでも日常生活でも友好的な関係を築くことが可能になります。だからこそ、私たちは言語を学び続けます。だからこそ、言葉によるコミュニケーションはドイツ語教育において重要な部分です。実際にドイツ語を話し、一緒に異文化と触れ合うときに必要な知識を身につけましょう。
