
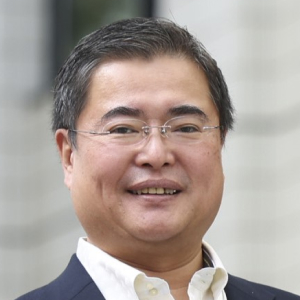
ロシアという国は興味深い(良い意味でも悪い意味でも)、ロシア語という言葉は面白そうだ、そう思うのならば、是非ロシア語学科の門をたたいてみてください。ロシアの言葉や文化はロシア政府とイコールではありません。むしろロシア・ソ連の人たちは言葉や芸術などの文化で政治と戦ってきた歴史を持っています。現在はロシア政府の言論統制によって戦いが見えにくくなっていますが、確実にそれは存在していると私は信じています。見えない形でロシアの政府と戦っているロシアの人々・言葉・文化を私たちは見捨てるべきではありません。あなたも勇気をもってロシア語学科で私たちと共に学んでみませんか?私たちは歓迎します。
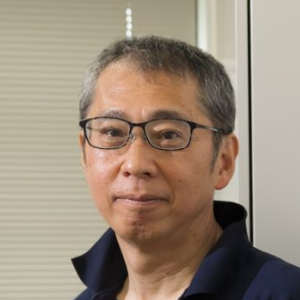
生命倫理は、科学や技術の発達の最前線で「生命とは何か」「人間とは何か」を問うきわめてエキサイティングな学問です。安楽死、自殺幇助、不死、クローン人間、遺伝子の改変、ゲノム編集、人間のサイボーグ化、トランスヒューマン(Transhuman)等々に関する問題が扱われます。人間のあり方、生命のあり方が根本的に変わっていく時代の中で、人間とは何かを問い直しています。生命倫理を学び、知的な刺激を味わいましょう。

「近くて遠い」といわれる隣国ロシアですが、ロシアに対する理解を深めることのできる、よりよい研究をみなさんが行えるよう、サポートしていきたいと思います。

ことばや、それに関わることであれば何にでも興味を持って対象の分析に取り組んでいます。 従前変わらずに追いかけているテーマとしては、人間が、ある動作やその場面全体をどのように認識・把握しているかをあらわす動詞の形の意味と用法についての分析です。 外国語という、母語以外の未知のことばを学ぶことを通じて得られる、全く異なる視点からのものの見方や捉え方に興味を持ち、外国語の学習・研究を楽しんでもらいたいと思います。

勉強はとても楽しい。浴びるように本を読み、飽きるほど映画を見、単語と文法をひたすら覚え、歴史と文学で無数の人生をたどり、理論と現場を往復し、ことばのあやつり方を身につけ、あたたかな笑みを絶やさないこと。そうすれば、世界水準のチャーミングさと、どこまでも深いロシア人との友情があなたのものになります。

私の研究分野は法律(租税法)です。特に、租税法の領域において、私企業に対する違憲又は違法な租税優遇措置の 司法機関による統制についての研究を続けています。また、最近、租税法以外の研究分野について研究を行うことに対して関心も高まりました。 比較法の観点から、日本の法、欧州連合におけるスペイン法及びラテンアメリカ法に関する包括的かつ多面的な研究を行うことを目指しています。

社会言語学と応用言語学を研究しています。特に、言語とアイデンティティの関係や少数言語の復興に興味があります。また、第二言語・外国語教育を批判性をもって考えることにも関心があります。一緒に言語研究が多様で公平な社会づくりにどう貢献できるか探求していきたいと思います。

上智の外国語学部で学ぶということや、自らが専攻する言語の高い運用能力を身につけることが社会的に期待されると思います。しかし、「英語がペラペラ」になることだけでは、グローバル化する世界で生き抜くには不十分です。多言語を通じて、国内外の歴史、社会、そしてそこに住む人びとについて学び、そして学んだことから自らが生きる世界を客観的に、多角的に捉える力を身につけてください。そして、自分が様々なグローバルな現象、グローバルに活躍する人びと、ときには取り残されてしまった人びとと繋がり、有意義な関係を紡いでいけるかについて、自分なりの答えを見つけてください。
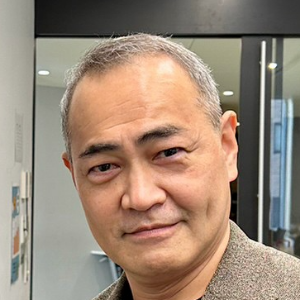
Second language acquisition is influenced by various factors—both internal and external to the learner—leading each individual to construct a unique linguistic system in their mind. The more we deepen our understanding of second language acquisition processes, the greater the range of possibilities for creative learning and teaching. At the same time, we may find ourselves becoming more tolerant and compassionate toward learners striving to improve their second language abilities. In other words, SLA is both a theoretical and practical field of study.

ポルトガル人が大航海時代以降、世界の様々な国や地域に残した言葉(=ポルトガル語そしてクレオール語)や文化を研究しています。グローバリゼーションの先駆者ともいえるポルトガル人の足跡を辿る旅には終わりがなく、しかも新たな「発見」に満ちています。知的好奇心と行動力にあふれた若者たちとの出会いを楽しみにしています。
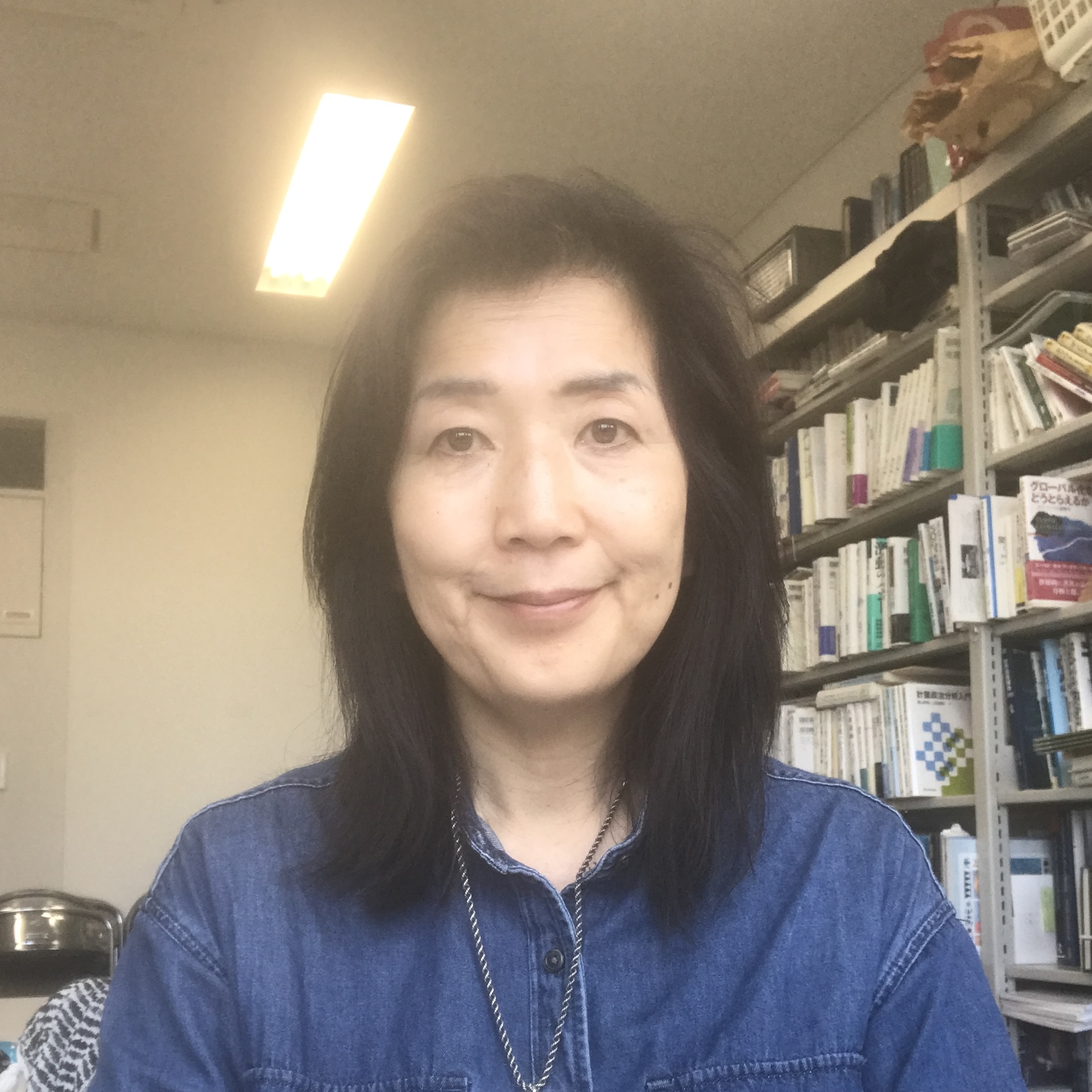
専門は北アフリカ、とくにチュニジアとエジプトの社会開発やマイグレーション、環境などですが、フランス語圏の中東アフリカ全般にも関心をもっています。フランス語圏の中東やアフリカにおける現代の諸問題や事象を探求したい方を歓迎します

I aim to try to turn my classroom into a space where students can discuss ideas and collaborate on creative projects. Often the creative projets are very playful and may seem quite child-like at first, but gradually they always lead us into discussions about important issues: the environment, democracy, freedom, fairness in society and consideration of our responsibilitiees towards other people.

I research British ideas of Asia during the eighteenth and nineteenth centuries, with particular focus on representations of the “East” in travel writing, material culture, and fiction. Publications include (with Tomoe Kumojima) Pacific Gateways: Trans-Oceanic Narratives and Anglophone Literature" (Palgrave, 2024); (with Alex Watson) "British Romanticism in Asia: The Reception, Translation, and Transformation of British Literature in India and East Asia" (Palgrave, 2019). I have also edited a special issue of Studies in Travel Writing (with Steve Clark, 21.1: 2017), focusing on the Victorian traveller Isabella Bird. I am one of the series editors of the Palgrave “Asia-Pacific and Literature in English” series. In 2025-26 I will be on sabbatical, working on a book project on utopianism and British writing on Japan.

16~17世紀のスペインの歴史を研究しています。中世の長いレコンキスタのなかで形成された多様な社会・国家・文化・言語・宗教をもった人々が、どのように「スペイン」というまとまりの国をつくっていったのか、それがどのように今でもこの国の多様性につながっているのか、という観点から研究をしています。
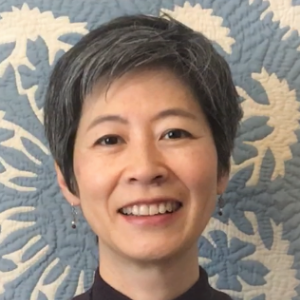
なぜ子供はどんな言語でも教わることなく自然に話せるようになるのか。この問に対して、「ヒトは全ての言語に共通する基礎知識を生まれつき持っているから」という仮説を立て、その知識の中身を解明しようというのが生成文法の研究です。あらゆる言語に共通する文法とは、どんなものなのか?多様な言語の比較分析から見出された共通する規則性をもとに仮説を立て、さらに別の言語のデータを用いて検証、その結果に基づいて新しい仮説を立てる…という科学的手法でこの問題に取り組みます。英語や日本語は勿論、様々な言語のデータから何が見えてくるか。謎解きの作業を通して、観察力、データ分析スキル、論理的思考力が磨かれる研究分野です。

言語を習得し、それを運用するとはどういうことを意味するのだろうか。言語行為論(speech act theory)というのがあり、それは言語を発話の<行為>として用いると、社会関係を維持させたり、覆したりする効力があるという考え方である。発話行為は権力関係が絡み合うという政治性があるため、どうすれば効果的に発話を成功させるかという問いがある。文学作品が綴る「物語」のなかには、発話を政治的なダイナミックなものとして捉えるものが多く存在している。19世紀以降のとくに発話の機会を奪われてきた女性やマイノリティの物語や発話について考えてみましょう。さまざまな物語や文学作品を介して「声」を捉え直せば、なぜ社会的弱者の沈黙させられてきたのか理解でき、その「声」を掘り起こす意義も感じられるのではないかと思います。

My specialty is Creative Writing and Contemporary Fiction. In my classes, I focus on how we can use language as an observational and interpretive tool to bring the world closer to us and how writers craft stories to explore issues present in contemporary life. To this end, I try to create space for students to think creatively and critically about their experiences and, ultimately, their place in society. Class projects focus on argumentative writing, the foundations of storytelling, and narrative perspective. We consider topics such as culture, immigration, assimilation, and equality. My classes aim to promote flexible thinking that encourages empathy and helps build acceptance for ourselves and others.

ドイツ語学科では、ヨーロッパ政治経済論とドイツ政治研究といった科目を担当しております。ヨーロッパの方はEUや構成国の歴史や現代の政治経済を、ドイツの方では、政治制度や昨今の事情について講義をしております。演習では、学生がヨーロッパやドイツの政治や経済に関する任意のテーマでゼミ論文や卒業論文の執筆を勧めております。研究テーマはドイツの政党や議会政治で、国会議員のリクルートメントや政党の活動を日本との比較を通して見ています。

音声学とは言語の音声に関わるメカニズムを科学的に探求する学問です。音韻論は、その中でも脳内で行われる処理を文法や語彙に関する他の処理との関連を考慮しながら追求しています。また、言語機能を支える人間の心理、生理、物理的な能力を総合的に考察するのが認知科学です。どれもがどこかでつながっていて切り分けるのが難しいのですが、一つの実験の中で扱える範囲をうまく切り出して意味のある結果が出せるように日々知恵を絞っています。

日本と国際的な立ち位置が類似し、多くの課題を共有しつつ、全く異なる対応を取ることが多いのがドイツ(語圏)です。なので、ドイツ語圏の社会について研究することは、異なる可能性を知って思考を柔軟にするためにも、日本の来し方行く末を考えるうえでも、きわめて意義が大きいと考えています。自分が関心あることを、ドイツ語圏を参照しつつ考えてみると、思わぬ発見があるに違いありません。